
�@
�@
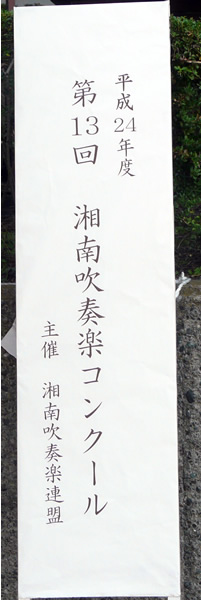
�����돋���B
�V���Q�U���A�Ǘ��l�̓R���N�[�����ł��銝����s��������ق���k���T���Ɉʒu����E��i�\���Z�j��������Ă������킯�����A���ɓ�������܂łɊ��ɑ�ʂ̊��B
���ɓ������ē����������ɍs���ƁA�u���Z�`����̊J��͗\����P�O���x��܂��̂ł������������v�ƌ���ꂽ�B
�i���Ԃ�A���Z�`�̑O�ɍs���Ă������w�`���傪���т��̂��Ɓj
���̎��A�����͌ߌ�S���P�O���B
�{���̊J�ꎞ�Ԃ͂S���S�T���ł��邩��A�܂��R�O���ȏ�͂���̂����A���ɕ��юn�߂Ă���B
�Ǘ��l�͊O�̌i�F�ł��B�e���悤���ƁA��ɂ͉���炸�A��ꂩ��O�֏o�Ă݂��B
��߂Ă����ׂ��ł������B
������A�N�\�����B
���̒��ł́A���w���Ǝv�������̎q����l��������ƍ��荞�݁A���̎q������������^���A������Ő�ł����Ă����i���ڂɓ���B
�y���M���ǂ��������B
�ŁA�Ǘ��l�͂ӂƋC�ɂȂ����B
���̂܂܊J�ꎞ�Ԃ��x�ꑱ����ƁA�J��҂��̋q�l�̗�͂ǂ�ǂ��Ȃ��āA�z�[���Ɏ��܂肫�炸�A�ǂ�ǂ�ƊO�q�����Ă䂭�ł��낤�A�ƁB
�i���ہA�Ǘ��l�͂���������ʂ����x���ڂɂ��Ă���j
���Ƃ��Ƃ̏����ɉ����A�r��Ȑl�����x�䂦�A��z�[����������O�܂ő����q�l�����͊F�A��q�E��������͂��߂Ƃ���u�蓮���͋@�v�Ŏ����q���A���N���ɕ��𑗂�A���l���̐l������������⋋���悤�ƁA�������̔��@��T���B
�Ǘ��l�͂��܂��ܗ␅�@�̂������ɕ���ł����̂ŁA�����ŗ₽���������ނ��Ƃ��ł������A���NJJ��͗\����R�O���قǒx��A�|���l���o�Ă��s�v�c�ł͂Ȃ���Ԃ��Ǝv��ꂽ�B
�ǂ���玖�Ȃ����悤�����A�R���N�[���͉^�c����̂��{���ɑ�ς��Ɗ���������ł���B
�Ǘ��l�������̂a������J�n���x��A�܂����炭�҂Ƃ����\�����@�m���A��������₽�����ݕ���p�ӂ����̂͌����܂ł��Ȃ��B
�i�����āA���ۂɂ����Ȃ����D�D�D�j
 �@
�@ �@
�@
�@
�@
���܁F�k�ˁA���員��A�Ó�
�@�����̂����A���員��ƏÓ삪������
��܁F���A������
���܁F�c��Ó�
�@
���ʂƂ��āA���員��E�Ó삪�����ւ̏o��ƂȂ����B
�������͂W�^�P�O�i���j�_�ސ쌧���z�[���ɂ�
�����Ă��āA���ƂȂ������Ȃ�悤�ȗ\�������������A���͂Q�Z�̎��R�Ȃ��g���㉹�y���h�ŁA�`�ł́i������a�ł��H�j���������e�C�X�g�̍�i�łȂ��ƕ]�����ɂ����A�����́A���Ȃ��Ƃ����������e�C�X�g�̊y�Ȃ̕��������]�����₷���Ƃ��������ꂪ����̂��ȁA�ƁB
�Ǘ��l�͏Ó쐁�t�y�R���N�[�����������Ă��Ȃ����߁A�Ó�n��Ŏ��ۂɉ��t�����Ȃ��A�S���̐��t�y�R���N�[���̏k�}���Ƃ��������𗧂āA����Ɋ�Â��Ęb�����Ă���킯�����A���������ꂪ�������Ƃ���A������Ƃ��Ȃ��C������B
�Q�N�O�̉āA�Ó썂�Z�����֓����ւ̏o��������l�������́m��������Q���n�A���ꂪ�Ó�炵���i�Ƃ������A�w���҂̏��V�Ă���炵���j�I���ł���A���ꂪ������邩�ǂ����͌X�̐R�����̋C�����̂���悤�ɂ����E�����ƍl���Ă����B
�܂�A����Ȍ����������Ă�������邩������Ȃ��̂����A�g�����h���t�y�ȁh�i�Ƃ��������������݂��邩�ǂ��͂��Ă����j�ɑ��ẴA���`�e�[�[�Ƃ������A�Η��̐ݒu�Ƃ������A���������Ӗ��̖����E�@�\������悤�Ɏv���āA�Ђ��傤�ɍD�܂������Ă����̂����A�������N�͉ۑ�ȇX����͂�g���㉹�y���h���Ă��āA�S�̂Ƃ��Ă�����ɌX���Ă���̂��Ƃ���������B
�ܘ_�A�Ǘ��l�̂��̐������Ⴂ��������Ȃ����A�ꎞ�I�ȁA�����͏Ó�n��ɓ��L�̕��y�I�Ȃ��Ƃ�������Ȃ��B
�P�ɂ��������Ȃ�I�w�Z���Z�p�≹�y�ʂł��D��Ă��������A�Ƃ������Ƃ�������Ȃ����D�D�D�B
���₢��A�Ȃ�����Ȃ��Ƃ������̂��ƌ����A���員��i���t�����Ó����j�̎��R�Ȃ������A�����u���`��A�Ó�ƃe�C�X�g���߂��v�Ɗ��m���A�u���`��A���̎�̊y�Ȃ������o�Ă�����A�I�C���ɂ͂��̑P�������͂����炭���f�ł��Ȃ��D�D�D�v�Ƃ����A������Ƃ����߂��݂Ɏ����C���������������Ȃ̂���B
�܁A��������̋Y�����Ǝv���āA�������ĉ������܂��B
�@
�@
�y�k�ˁz�R���g���o�X�R�{�A�j�q�U��
�@�ۑ�ȇW�@�s�i�ȁu��]�̋�v�i�a�c�M��ȁj�@ �@
�@���R�ȁ@���ȁu�ӓ��Ձv�i�`�D�h���H���U�[�N��ȁ^��؉p�j�ҋȁj
������镗�i���A����Ă�킸�A��������ƂP�����y�ɂ��Ă������Ƃ����C�������`��鉉�t�B
�u���ˎ�ˋ��v�̗���A���ɏ�ʓ]���ł̎�t�����������ǂ���Ƃ����ӎ������邽�߁i���Ԃ�j�A�������k���āA�}���̌��������t�͑f���炵�������B
���O��ށm�ڂ������������n�����Ă�����Ă����̂ŁA�T�b�N�X�̓����̑����ɂ������Ƃ��A�g�����y�b�g�̓n�ӂ��u�y�����v���t���Ă��邩�ǂ����A������ƋC�|���肾�������A���Ȃ��Ƃ��Ǘ��l�ɂ͂悢���t�ɒ���������B
�y���員��z�R���g���o�X�P�{�A�j�q�T��
�@�ۑ�ȇU�@�s�i�ȁu��낱�т֕��������v�i�y��N�i��ȁj
�@���R�ȁ@�E�B���h�I�[�P�X�g���̂��߂̃}�C���h�X�P�[�v�i��������ȁj
�ۑ�ȂŁA�؊ǂ̃s�b�`�����C�ɂȂ��ʂ����������A�n�������ɂȂ�قǁA�D�����C�����ɂ��Ă���鉉�t�������̂ŁA���R�Ȃւ̊��Ҋ����Ђ��傤�ɍ��������B
�����āA���㉹�y�I�v�f�𑽕��Ɋ܂��R�Ȃ��A���̊��҂ɔw�����ƂȂ��f���炵���f�L�ł������B
�e���|�ω��ɉ����鍂���V���N�����ɂ��A�����҂̋C������h���Ԃ�A�����r�ꂻ���ɂȂ�Ƃ�������肬��Ōq���ł䂭�悤�ȃC���[�W�ŁA�Ђ��傤�ɑf���炵���Ɗ������B
Sudden Death�I�ȏI�����ƁA����ɑ����u�����v�ˁu��v����A�̗���Ƃ��āA���Ȃ���K��ς�ł����悤�Ɍ����A�r�W���A���I�ɂ��y���܂��Ă��ꂽ�B
�����Ɍ����ƁA�����I�ɂ͂�����ƎG�Ȋ���������Ƃ�������������A�����ɐi�߂邱�ƂɂȂ����̂ŁA�����������P�_���C�����邱�ƂŁA�����ƍ����]������̂�������Ȃ��B
�@
�@
�y���z�R���g���o�X�Q�{�A�j�q�R���H
�@�ۑ�ȇW�@�s�i�ȁu��]�̋�v�i�a�c�M��ȁj�@ �@
�@���R�ȁ@ �p���h�[���̔��i�����V���i��ȁj
�w���҂̊ێR���搶�i�ʏ́E�Ƃ��邿���j���u�p���h�[���̔��v�̉��t���R�x�ڂŁA���ߓx���オ�������Ƃ��M�킹�鉉�t�ɂȂ��Ă����B
���ɖ`���́A�����̂������̂����������Ƃ��납�班�����߂Â��Ă���l��A�}�C�i�[�̏�ʂł̋�����`���鉹�A�Ō�̃e�[�}����̋�����悤�ȓW�J�́A�����Ă��Ē��������قǂł������B
�Ŋy��̃V���N�����̍������A�������x���Ă���A�Ђ��傤�Ƀo�����X�̂悢���t�������B
�y��z�R���g���o�X�Q�{�A�j�q�P�R���H
�@�ۑ�ȇX�@���藧���߁i�����~��ȁj�@ �@
�@���R�ȁ@ �f�B�I�j�\�X�̍Ղ�i�e�D�V���~�b�g��ȁ^�����_�s�ҋȁj
�ۑ�Ȃ̑I�����炵�āA���ɏ��V���[���h�S�J�ƌ�����B
�i�ۑ�ȇX��I�̂́A�Ó���܂ߐ_�ސ�ł͂U�Z�̂݁j
�����āA�ܘ_�A���R�Ȃ����㉹�y�e�C�X�g����u�f�B�I�j�\�X�̍Ղ�v�B
���Ԃ�A�ƂĂ��I���̂��Ȃ��Ǝv���̂����A�ǂ̂��炢�I���̂��A�Ǘ��l�ɂ͌����������B
����͊Ǘ��l�̎v�����̒�Ăł��邪�A�Ó썂�Z�͂��̎��Ă�Z�ʂ�艉�╶���ՂȂǂ̎��R�ȉ��t����������ʂŁA����͂Ǝv����f����w�i�ɗ����Ȃ���A�������N�̃R���N�[�����R�Ȃ�����Ă݂Ă͂ǂ��������H
�����炭�A�R���N�[���Ƃ͂܂�������Ó썂�Z�̑��ʂ���������̂ł͂Ȃ����Ɗ��҂��Ă��܂��B
�y������z�R���g���o�X�R�{�A�j�q�U���H
�@�ۑ�ȇW�@�s�i�ȁu��]�̋�v�i�a�c�M��ȁj�@
�@���R�ȁ@�p�b�T�J���A�ƃg�b�J�[�^�i�����O�a��ȁj
�Ǘ��l�I�ɂ͋��܂ł��悩�����̂ł́H�Ǝv�����t�������B
�m���߂��킯�ł͂Ȃ�����A���Ƃ������Ȃ����A�u�V���v���Ɂv�u�\������āv�Ƃ����e�[�}�����݂��Ă����̂��Ǝv���قǁA�w���ҁE����T�q����ƕ��������̈ӎu������Ă���f�G�ȉ��t�������B
���Ɏ�t�����璆�ԉ��ʂʼn��t�����ʂŁA�P�P�̉����J�Ɉ������Ƃ���p���A�ቹ�ŗh���Ԃ���|�����ʂł̑������Ƃ��������̂��G�킾�����Ǝv���B
�Ǘ��l�����ɂ́u�V���E�����a�����H�v�Ə�����Ă���B
���Ƃ���܂ł������ɂ��Ă��A�����鉹�y�ɑ���A�v���[�`�͑����ė~�����Ȃ��B
�@
���܁F����A�����A�ߗ�
�@�����̂����A����ƒߗ䂪������
��܁F�Ó�w��
���܁F���l�A�A���Z�C�A
�@
�������͂W�^�P�P�i�y�j���s���當����قɂ�
�Ǘ��l�̍ő�̋����i�ƌ����ƁA����������ł����j�͓����̖��i�ł������B
�o�������A�D�����i�H�j����̒���Ƃ������Ƃ������āA�v���b�V���[������̂ł́H�Ǝv���Ē����Ă������A���t���I��������Ƃ́A�u����A�����ł���v�i�Ǘ��l�����ɂ��j�Ƃ�����ۂł������B
�ڂ����͌�q���邪�A�Q�O�O�X�N�͓��܁A�Q�O�P�O�E�Q�O�P�P�N�͋�܂ƃX�e�b�t�A�b�v���āA���̉Ĉ�C�Ƀu���C�N�����B
�����ɍs���Ȃ��͎̂c�O�����A���̐�����ۂ��ė~�����Ǝv����o���h�ł������B
�܂��A�P�ʒʉ߂��ʂ���������́A�����炭�ނ�̐�Ε]���̒��ł͂���قǂ悢�_���������Ȃ����t��������������Ȃ����A����ł��g�b�v���Ƃ������Ƃ́A�x�[�X�̕����łǂꂾ���A�h�o���e�[�W������̂��ƁA��ȂƂ���Ŋ��S�����B
�@
�@
�@�E�B�Y�E�n�[�g�E�A���h�E���H�C�X�i�c�D�q�D�L�����O�n����ȁj

���c����ƕ����̋v�ш�����
�u�݂��Ƃ��Ȃ����t�ł��݂܂���B�����ĂȂ����A���͏o�ĂȂ����B�܂��܂������Ă���͂��o����Ă��܂���ˁB�v
���є��\��A�W�ҒʘH�ʼn�����u�Ԃ̌��t�ł������B
�ނ�͏��ڎw�����Ƃ���ӎ����������߁A����̉��t���炢�ł͖����ł��Ȃ��Ƃ������������肠��B
����ł��P�ʒʉ߁A�Ƃ����̂͑債�����́B
�Ǘ��l�����ɂ́u�}���߂̉��ʁH�v�u�ׂ��ȉ��Ɖ��Ƃ̌q����Ɏ���P�̗]�n�H�v�u�~�X�g�[���H�v�Ƃ��������t�����������Ă���B
�Ǘ��l�͊��쐁�t�y���̃t�@���ł���A�ނ炪���낻�댧���̕ǂ�ł��j��A�܂����֓����ɐi�o���Ă���邱�Ƃ�ؖ]���Ă���̂ŁA����������������̂����i���Z�̃����ɂ͂����������������_�͂��܂�o�Ă��Ȃ��j�A���ꂪ�����҂��Ƃ����ƌ������A�Ƃ������Ƃł��낤�B
�����̋v�т����
�u�_���ȉ��t���������ǁA�����ɏo���ăz�b�ƂĂ��܂��B�{���͋��܂����炦�Ȃ����Ǝv���Ă��܂����̂ŁB����ł��̃����o�[�ł��������ꏏ�ɉ��y���o���Ċ������ł��B�ڕW�͓��֓����o��ł��I�v
�Ɣ��Ȃƕ������q�ׂĂ���܂����B
�ܘ_�A�Ǘ��l�����ɂ́u�s�������n�܂�v�u�]�����ł̋���_�C�i�~�N�X�v�u��t�̋��ǂ��ꂢ�v�u�Ō�A�n�ꂩ��N���オ�鉹�A�唗�́A�����v�Ƃ������_�ߌ��t������ł���B
���ꂾ�����������ȕ]�����ł���A�Ƃ������Ƃ͌����Ɍ����Ẳۑ肪�\���킩���Ă���A�Ƃ������ƂȂ̂ŁA�t�Ɋ��҂��Ă��܂��B
���[���A�F�Ŋ��҂��悤�B
�y�����z�R���g���o�X�O�{�A�j�q�U
�@��̌��u���ݕv�l�}���c�@�v�Z���N�V�����i�d�D�J�[���}����ȁ^��؉p�j�ҋȁj
�����댩�Ă��Ă��y���������B
�Ŋy��̎g�����̃o���G�[�V���������ʂŁA�����炭�͑Ŋy��ꑮ�����o�[�����ł͑���Ȃ��̂ŁA�NJy�탁���o�[������ւ�藧���ւ��Ŋy������t����B
���̗l�̓r�W���A���I�ɂ��ʔ������A���Ƃ��Ă���������Ǝ��Ȏ咣���Ă����B
�܂��A���������E�C�P�C�P�̉��y�ł͂Ȃ��A�ׂ��ȕ��������J�ɂ������Ƃ���ӎu������������o���h�������B
�I�Ղ́A��u����ŏI��肩�ȂƎv�킹�����ƂɁA�܂����t���n�܂�A�����č��x�͖{���ɏI���A�Ƃ����h���}�`�b�N�ȓW�J���Ǘ��l�̃c�{�ɛƂ���̂ł������B
�w���҂̗��n�T����Ƃ͖ʎ����Ȃ��̂����A����A������������͂������o���w���𑱂��Ē��������v���B
�����ɍs���Ȃ������͎̂c�O�����A�܂��܂��L�т�]�n�̂���o���h�Ȃ̂ŁA�n���ɁA�y�������t�����Ă����ĉ������B
�y�ߗ�z�R���g���o�X�P�{�A�j�q�R���H
�@�t�@�C���[�X�g�[���i�r�D�u����ȁj
�ȑO�A���l���w������Ă����n�ӗǎq�搶���ߗ䕋�C�Q�N�ڂŁA���悢��R���N�[���ɁB
�ǂ������F�̉��y�ɂȂ�̂��A�y���݂������B
�o�����X�ƃV���N�������d�����邹�����A�S�̓I�ȃ_�C�i�~�N�X����������������Ƃ�������������A�Ђ��傤�ɂ悭�܂Ƃ܂��Ă����ۂŁA���������Ӗ�����͓������������Ă���悤�Ɏv�����B
�r���̃T�b�N�X�E�z�����E�g�����{�[���i�~���[�g�j�̊|�������Ȃǂ́A�o���h�Ƃ��Ă̖ʔ������\���������Ă��āA�悢�Ȃ�I��ł���Ɗ������B
�܂��A�R���g���o�X�i���Ԃ�j�̎q�j�̋|�����Ɏv�����肪�����A�o���h�̏�����������Ɨ\�������Ă���鉉�t�������B
�@
�ߔN�A�j���̈ߑ��𑵂���`�[�����������W�ŁA���m�ɒj�q�̐����J�E���g�ł��Ă͂��Ȃ���������Ȃ����A�`�E�a������P�Q�`�[���ŃX�e�[�W�ɏ���Ă����Ǝv����j�q�͂U�P���B
�����Ƃ��ẮA���q�̂V���̂P���x���B
�j�q�̉��y�D�����A���t�y�������y���y����I�ԌX��������炵���A���̗�����~�߂�ɂ́A�Ƃɂ����S���ɂQ�E�R�N�����������������u���ĐV�P�N�̒j�q��A��Ă��邱�Ƃ��낤�B
���ہA���썂�Z�ł͍��N�A�V�P�N�̒j�q���P�O���߂��l�����Ă���B
�j�q�����������萔�ȏア�邱�ƂŁA�v����̂悳�����܂ꂽ��A�_�C�i�~�N�X�ω������₷���Ȃ邾�낤���A�����y������Ȃ��́H
���N�A���������j�q�����������Ă��邱�Ƃ�O���D�D�D
����ł́A�����ւ̏o�ꌠ���`�[���̕��X�A���X�����ł����A�M���ǂɋC�����A��������ڕW�𗧂ĂĊ撣���ĉ������ˁB
�S���牞�����Ă��܂��I